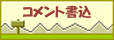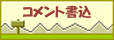淡路旅行2日目朝、洲本城跡を訪れた。
駐車場のある馬屋(月見台)から、家族は天守に先行させ、急ぎ足で東側エリアを探訪し、天守で合流後、
西側から南の丸経由で戻り、最後に大手門を拝んで、駐車場に帰ってくる経路を採ります。
|
 |
前日夕方、
天守もどきを大浜海水浴場から見上げる。
(ズーム!)
|
 |
駐車場にある案内板。
|
 |
南の丸方面に向かう途中の石垣。
|


|
南の丸隅櫓跡。
二重稜線の石垣になっています。
←マウスオンで、
新しく追加された石垣が分かります。
櫓を建てる為に追加されたのでしょうか。
|
 |
右を向くと...
櫓門でもあったでしょうか?
|
 |
上記門?を潜って左手の南の丸の石垣。
|
ここから東一の門を目指し、東進します。
|
 |
日月の池。
右奥に井戸も見えます。
|
 |
鉤型になっている東二の門。
形状からいけば、
左右の石垣間に門があったと思われますが、
舗装路のせいで礎石などは確認出来ません。
|
 |
東二の門を潜って振り返る。
|
 |
武者溜。
|
 |
東一の門。
|
 |
そこの石垣。
野面積みの古いものの様です。
|
ここから引き返して、東の丸を経由して本丸を目指します。
東の丸は、郭図には東二の門を西に入った辺りを示していますが、
ここでの紹介では、その北の何段にもなった郭群を示すものとします。
|
 |
東の丸高石垣。
|
 |
東の丸北東の角。
|
 |
東の丸に上がって、洲本城で一番古い石垣。
|
 |
上記右奥に続く。
|
 |
東の丸最上段。櫓台かな?
ここに「東の丸二段曲輪」とある。
|
 |
その櫓台?の西側の郭。
東の丸主郭といっていいのかな?
|
 |
その淵の石垣。
|
 |
そこから北側の帯郭を見下ろす。
|
 |
西側へ一段下がって、先程の郭方面を向く。
|
 |
そこから西側に虎口を潜って、振り返る。
|
 |
八王子木戸。
|
 |
東側から本丸を見上げる。
|
 |
本丸への大石段。
|
 |
大石段を登ると、先に虎口が見える。
|
 |
この虎口も鉤型になってます。
この左の石垣から奥に向かって門があった様で、
その礎石が残っている様です。
|
 |
虎口を潜って、本丸にある武者走台。
|
 |
武者走台の上から天守を望む。
|
 |
そして本丸を見下ろす。
|
 |
天守東側の台上に上がりました。
|
 |
そして、東下の郭を見下ろす。
その郭の左奥が八王子木戸。
更にその奥が東の丸。
|
 |
洲本港方面を望む。
水軍の城らしく海辺にそびえてます。
中央右奥に、
昨日遊んだONOKOROの観覧車が見えます。(^^)

|
 |
左を向くと洲本の市街地を一望。
|
 |
天守もどきを見上げる。
昔は上に上がれた様ですが、
今は老朽化の為、階段が撤去されています。
|
 |
西側の虎口から本丸を出る。
ここも鉤型になっていて、
左右に門跡の礎石が見えます。
|
 |
虎口を出て、振り返る。
中央に鏡石が見えます。
|
 |
天主台の南西角。
|
 |
天主台の北西角。
|
 |
本丸西の通路から天守を仰ぐ。
|
 |
本丸から南西方向にある郭。(南の丸の西側)
|
 |
その西側は土塁になっています。
その向こう側(下)は石垣になっているので、
石塁が崩れたのか?元々土塁か?
|
 |
南の丸。
|
 |
南の丸の南面は石塁になっています。
左奥が例の二重稜線の櫓台(隅櫓)になります。
確認しませんでしたが、
先の土塁がある郭(右後方)から、
左奥の櫓台まで続いている様です。
|
 |
周回して来ました。
最後になるが、大手門を出て振り返ります。
|
 |
その横にある案内図。
|
 |
本当に最後になるが、
駐車場横にある馬屋(月見台)。
|
 |
そこから南東側の海岸線を見下ろす。
|
今回、西の丸方面は未踏です。
ここはとにかく石垣の多い城跡で、見所は満載!
時間があれば、西登り石垣、東登り石垣なども巡ってみたい所です。
(洲本城)
三好氏の重臣、安宅治興の築城。
信長から毛利氏に寝返った、当時城主(4代)だった安宅清康を羽柴秀吉が討伐。翌年、清康は城を明け渡す。
仙石秀久、脇坂安治と城主を替え、関ヶ原合戦で徳川方に寝返った脇坂安治が伊予に移封(加増)後、
池田忠雄が淡路国領主になった。その際に洲本城は廃城となり、岩屋城、由良城と本拠を移す。
大坂の陣(夏の陣)後、徳島藩主である蜂須賀氏に淡路国を加増、蜂須賀家家老の稲田氏が由良城代となる。
後、由良城を廃し、再び洲本城に本拠を移す。
以後、稲田氏が代々城代を務め、明治維新後に廃城。
洲本城の歴史(本丸説明板より)
|